この間の当時の美濃路★は,一里塚★/岐阜街道★の追分★/立場★と続いているところ始まって,ところどころに寺や神社を交じえながら,家並がほとんど絶え間なく続いていました。そのためもあって都市化の影響をあまり受けなかったようで,今でもところどころに街道の面影★が残っています。この間には,一里塚の跡/岐阜街道の追分にあった道標★/長光寺/北市場美濃路公園/立部神社と山車蔵/亀翁寺など,近くには清須代官所跡/総見院などがあります。
この間の当時の美濃路★は,一里塚★/岐阜街道★の追分★/立場★と続いているところ始まって,ところどころに寺や神社を交じえながら,家並がほとんど絶え間なく続いていました。そのためもあって都市化の影響をあまり受けなかったようで,今でもところどころに街道の面影★が残っています。この間には,一里塚の跡/岐阜街道の追分にあった道標★/長光寺/北市場美濃路公園/立部神社と山車蔵/亀翁寺など,近くには清須代官所跡/総見院などがあります。

見取絵図★を見ると,確かにこのあたりに北側の一里塚★があって,北側の一里塚は旧井之口村(現在は稲沢市井之口町池向)に属し,南側の一里塚は旧六角堂村(現在は稲沢市六角堂西町)に属していたようです。
写真右端に,あとで取り上げる四ッ家追分の石碑が写っています。
 A ↗ 2021-03
A ↗ 2021-03
 B ↖ 2021-03
B ↖ 2021-03
私の知るかぎり,空地になっている角には食料品店がありました。もう半世紀ほども前のことです。店の前に大きな道標があったら,きっと邪魔だったでしょう。そこで「もしかしたら,道標は土地に余裕がある右の方の角に移されていた可能性がある。」という思いがわいてきました。自動車にぶつけられたとき,はたして道標はどこにあったのでしょうか。そこでいくつかの資料を見ましたが四ッ家追分にあった道標はダンプカーの接触で破損したため,長光寺に移したというようなことは書いてあっても,道標があった位置については書いてありません。
道標の位置について,手持の資料からもネットからも手掛りが得られなかったので,古い航空写真で調べたところ,昭和36年(1961年)撮影の航空写真(国土地理院)にそれらしいものがありました。やはり右の方の角です(赤円内)。左の方の角は,道路ぎりぎりまで建物があるようです。
すでに取り上げた「稲葉宿にあった津島へ向かう道の道標」もそうですが,邪魔だということで移されてしまった道標は,けっこうあると思われます。
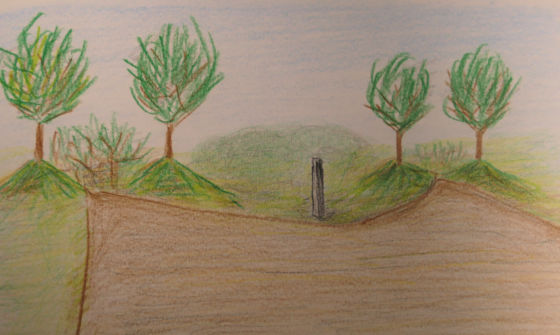
ここは県道155号線(井之口江南線)の始点になっています。
見取絵図を見ると,古民家★が建っているところから始まって,東に数軒の立場★が並んでいます。ここにあった立場は,名物の「四ッ家うどん」を味わうことができたと伝えられています。
 B ↗ 2021-03
B ↗ 2021-03
岐阜へ向かう鎌倉街道 後
の岐阜街道と 稲葉 萩原
起を過ぎて 垂井へ向かう
美濃街道との分岐点である
昭和四十四年五月
稲沢市
 D ↖ 2021-03
D ↖ 2021-03
盤桓子と號す 安永二年 西 暦 一 七 七 三 ここに
生れ 鈴木朗に學んで尾張藩の右筆
となる 天保十二年 西 暦 一 八 四 一 に没す
長光寺に葬る
昭和四十四年五月
稲沢ロータリークラブ
 D ↘ 2021-03
D ↘ 2021-03
 E → 2020-12
E → 2020-12
 F ← 2020-12
F ← 2020-12
この道標が,鉛筆マーク C で示した本来の場所にあったときは,刻まれている文字が正しい方向を示していたことがわかります。
いくつかの資料には「文政2年,西暦1819年」というように書いてありますが,文政2年12月は西暦1820年1月になる可能性が高いです。己卯は文政2年の干支です。

 A ↘ 2020-12
A ↘ 2020-12
役所橋跡
江戸時代中期、この橋の北東、
現在の清須市分地に尾張藩の清須
代官所(陣屋)が構えられていた。
美濃街道六角堂村集落と代官所と
を結ぶ役所道がここを通り、この
下を流れる古川用悪水路に役所橋
が架けられていた。
稲沢市教育委員会
役所橋は今では味気ない橋ですが,「少し前までは古いコンクリートの橋でした。役所橋って書いてありました。」ということを聞いたので「Google Street View」で調べたところ,2012年3月に撮影したものがありました。説明板はまだなかったようです。
見取絵図★には木々に囲まれた屋敷の中に建物がいくつか描かれていて,尾張殿地方役所と添えてあります。
 B ↗ 2020-12
B ↗ 2020-12
 C ↙ 2021-03
C ↙ 2021-03
美濃路の由来
美濃路は、天正年間(今から約400年前)織田信雄が幅5間(9m)の道路に改修させたのが始まりで、東海道と中山道を結ぶ重要な脇街道であった。
宮の宿(熱田)で東海道と分かれて、名古屋・清須(清須市)を経て北市場地内を通り、稲葉・起・墨俣・大垣の各宿を経由して垂井宿で中山道に合流する。その里程は14里24町15間(57.6km)といわれた。
この道は慶長5年(1600年)の関ヶ原の役にも重要な役割を果たした。即ち東軍の先鋒として福島正則がこの道を西に進み、さらに勝利をおわめた徳川家康がこの道を通って凱旋した。家康凱旋路、天下統一に因み、江戸時代にはこの道を吉例街道と呼び、江戸・京都間の往来に盛んに利用された。
※なぜか萩原宿が抜けています。
 C ↘ 2020-12
C ↘ 2020-12
 D ↑ 2020-12
D ↑ 2020-12
稲沢市指定有形民俗文化財
山車 二軸
毎年七月第三または第四土曜日
に行われる「こがし祭」に引かれ
るもので、元来は津島神社と同じ
川祭で五条川の枝川に浮かべた船
であったが、枝川の廃川に伴い陸
上で引く山車が新調された。
高さ四mを測る。
昭和五〇年四月一日指定
稲沢市教育委員会
左にある立部神社は,明治維新前は牛頭天王社といわれていました。見取絵図★にも,牛頭天王と添えてあります。
 E ↘ 2021-03
E ↘ 2021-03
立部神社の読みですが,ネットで調べたところ,「たてぶ/たてべ/たつぶ」など様々です。近くに日下部町立部という地名があるので,立部神社の可能性もあります。
 F ↙ 2021-03
F ↙ 2021-03
 G ↖ 2021-03
G ↖ 2021-03
見取絵図★には,虚空蔵堂と添えてあります。
 A ↑ 2021-03
A ↑ 2021-03
白峰山 亀翁寺 曹洞宗
後小松天皇のころ(14世紀末〜15世
紀初め)の創建で、享保17年(1732)
まで亀翁寺と称したが、寺号を春日井郡
下原新田の薬師堂に譲り、虚空蔵堂と称した。
昭和17年(1942)旧号に復した。
重要文化財
木造虚空蔵菩薩坐像 1躯 南北朝時代
稲沢市教育委員会
説明板があるところは稲沢市ですが,総見院は清須市にあります。
 B ↘ 2021-03
B ↘ 2021-03
信長の菩提寺総見院
清洲町の北端にあるこの寺は、最近
まで、この美濃路から「織田信長公由
緒地」の石柱碑と参道が見られた。
この寺は、清洲城主時代の織田信雄
が父信長の菩提寺として、桑名大嶋の
安国寺を引取り、総見院を建てたのが
始まり。清洲越しで名古屋大須に移っ
た後、一六四四年、総見院第三代和尚
の隠居所を兼ねて、尾張藩祖徳川義直
が清洲の旧地に総見院として建てさせ
たものである。
信長、信雄、義直の位牌や、信長、
義直の墓碑を祭る。本能寺の変直後に、
信雄が探し当てたという信長着用焼兜
が保存されている。
美濃路まちづくり推進協議会
十字路の一角に,かつては松の木と,興聖山總見院と彫られた寺標★,それに説明板がありました。
 C ↖ 2020-12
C ↖ 2020-12
 D 2020-12
D 2020-12
彫られた字を當寺大檀那信長公大居士台雷王と,なんとか読んでみましたが,「雷王」は違っているかもしれません。ところで「台」という漢字ですが,現在は「臺」の新字体★として,たとえば「土臺」を「土台」と書くように,よく使われていますが,ここにある「台」は,敬意を表わす意味で古来から使われている本字★です。
見取絵図★では,総見院と美濃路を結ぶ参道があって,山門★は美濃路の方を向いていました。1946年撮影の航空写真(国土地理院)を見ると,やはりその参道があるように思われます。
 E ↘ 2021-03
E ↘ 2021-03
